たまに閃いて、
考えがどんどん広がってしまうことがあって。。
そういうのを書いてみよう。
以下全部極論だけど、書いてみる。
意味わからなかったら、読み流してください。
1月17日
18:00~21:00
場所:小豆沢体育館
参加者:ツッチー、萩原、タカC、こーへー、ととき、トミー、ゆうと、ワカ様、おくだ、ふかい、カズキ、ホッシー
”悪いボールの奪われ方”からの失点の締める割合ってどれくらいだろう。
そもそも”悪い奪われ方 ”の定義ってなんだろう。
大きく分けて指標値としては、“位置”と“取られ方”かなって思う。
□前提
前提として。
フットサルは相手に奪われることが無ければ失点はしない。(但し、オウンゴールは除く)
だから、
(失点の数)=(ボールを奪われた回数)×(変数)
だと思ってる。
事実、先日の都リーグ世田谷との試合は、
得点シーンも失点シーンもいわゆる”位置”と“取られ方”のまずさが、
大体の原因/要因でした。
あるチームがゲームの中で平均50回ボールロスとして6失点する場合、
ボールロストの数を25回にすれば3失点で済むはず。
3-6で負けていた試合は、
ボールロストを半分にすれば、
ボールロスとしない分得点機会が増えるとして、
4-3にひっくり返ると思われる。
□“位置”という考え方
さて、例えばフットサルコートを3分割して以下を数える。
α=(相手ゴール前の位置で奪わた事象)
γ=(味方ゴール前の位置で奪わた事象)
そうすると、失点の数は以下でしかない。
(失点の数) =(事象αの回数)×(事象αが失点に繋がる確率)+(事象βの回数)×(事象βが失点に繋がる確率)+(事象γの回数)×(事象γが失点に繋がる確率)
当たり前だけど大事。
□“取られ方”という考え方
さてこれは“位置” という考え方よりも、事象の切り分けが複雑だからな分もっと難しい。
ターンオーバー(wikipedia記)
意味:アメリカンフットボール、バスケットボール、ラグビーなどのスポーツで攻守が入れ替わること。
ターンオーバーを例えば以下で考えてみる。
A=(味方のシュートで終わる事象)
B=(味方のミスでキックインとなった事象)
C=(インプレー中で相手と完全に体を入れ替えられて奪わる事象)
D=(インプレー中でC程じゃないけどがっちり奪わる事象)
失点の数はさっきと同じ。
(失点の数) =(事象Aの回数)×(事象Aが失点に繋がる確率)+(事象Bの回数)×(事象Bが失点に繋がる確率)+(事象Cの回数)×(事象Cが失点に繋がる確率)+(事象Dの回数)×(事象Dが失点に繋がる確率)
#いわゆるMECEという考え方が難しい。。。
□さて
ここまで書いてみて、結局言いたいのはひとつ。
自分のワンプレーがどの程度味方チームの失点に影響しうるのか。
それを理解することが大事かなって最近思う。
単純なミスでボールを奪われたとき。
でも失点に繋がらなかったとして、
それは確率の問題であって何回かやってたら失点に繋がる。
“失点に繋がらなかったけど、危なかったね”っていうやつ。
なんにも貢献できていないとか、
ゲームに影響していないとか、
一見そう思ってしまうある個人のワンプレーが、
チームの結果に影響してるんだと感じる。
これ以上書くと、
書き過ぎなのでやめておく。
□さらに考え方を広げると
例えば、この日の練習試合のビデオ解析すれば。。
どの時間帯で、取られた“位置”と“取られ方”が、
どのパターンで何回あったか数えてみれば。。。
失点との相関が見えるかも。
この日の試合だけじゃなくて、サンプル数を増やせば、
チームとして何をすればいいか見えてくるかも。。
いわゆるビッグデータの使い方かなって思います。
スポーツにそれを適用する方法はそういうところにあると考えてみたり。。。
□最後に
もう一回言うけど、極論での考え方です。
いじょー。

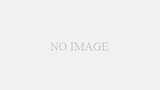
コメント
東工大の人ってこういうの好きだよね
そうなの!
言ってることはみんなと一緒!