筆者は自分の浪人時代の予備校の数学講師です。
『東工大数学』っていう授業を受け持っていた気がします。
たしか東工大出だった気がします。
本人のHPによると今も東工大にいるようなことが書いてあります。
 |
2112年9月3日、ドラえもんは本当に誕生する! (ソフトバンク新書 49) (2007/09/15) 桜井 進 |
「四次元ポケット」「タケコプター」「どこでもドア」…、子供のころ、誰もが憧れたドラえもんの世界は、けっして“夢物語”ではない。理論的にはすでに多くの科学者によって証明され、あとは科学の進歩により、それを実現化させるのを待つばかりといっても過言ではないのだ。本書では、話題のサイエンス・ナビゲーター・桜井進が、相対性理論、四次元、宇宙など『ドラえもん』に描かれた驚きのサイエンス・ワールドを紹介するとともに、ドラえもんから見えてくる近未来の予想図、そして彼のメッセージに迫る。
タイトルからすると、
『空想科学読本』的なものかという印象を受けるけど、
そういうんじゃないです。
量子力学の話なんかが出てきて、
それはつい最近大学院の授業で出てきた話とかぶったりしていたので、
楽しく読むことができた。
他にもドラえもんの道具から発展させた、
理学的なおもしろい話がたくさんで、
期待以上の作品でした。
作中にあったお話をひとつ。。
○人生の折り返しは何歳か?
たとえば100歳まで生きる人間にとって、
人生の折り返しは半分の50歳か。。
これはなんか違う。。
年をとるごとに一年の早さは短く感じるようになるものだ。
その理由としてのひとつには、
人は自分が生きてきた年数と比較して1年の長さを感じるから。
が挙げられるそうです。
つまり70歳の人にとっては、
生きてきた70年と比較して1年365日というのは、
たったの70分の1なわけ。
5才児にとっては、
生きてきた5年と比較して1年365日というのは、
かなりの長さに感じるわけ。
そーなると、
人生の折り返しは相加平均で考えるのではなく、
相乗平均で考えるべきなんだって。
だから、仮に4歳から記憶をもって100歳まで生きたとすると。
だって。
20歳が人生の折り返し。
…もう過ぎちゃったね。
おわり。

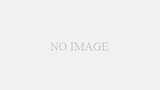
コメント