夜分遅くに活動でした。
日曜日の19時前に家を出て、ボールを蹴りに行く。
ばーかー。
日曜日の19時前に家を出て、ボールを蹴りに行く。
ばーかー。
4月22日
20:00~22:00
場所:ミズノフットサルプラザ味スタ
練習試合vsCRR
参加者:
えちご、いっちょさん、萩原、つっちー、たかC、シュウ、いなちゃん
昨シーズンfrontierZ練習試合やった回数ランキング1位の相手さんでした。
今シーズンは初顔合わせ。
全体通した練習試合の雰囲気としては、思ったよりバチバチしたな。っていう。
緊張感と激しさの狭間。
うちの反省は兎にも角にもまずはディフェンス面、マークに対する責任が弱かった。
いつも何とかしのいでる当たりなのですが、カテゴリーや個人能力の差がある相手だとやっぱり漬け込まれる。
終盤は特に失点を重ねました。
終盤は特に失点を重ねました。
各自ひとりが相手ひとりだけを捕まえる。というスタンスだとやっぱりキツい。
最低でも、相手ひとりとプラス他ひとり(orスペース)捕まえられる余裕を持たないと。。っていうのがミーティングで出た話。
意識だけの話じゃなくて考え方かと。
もう結構前から言ってるところ。
もう結構前から言ってるところ。
次はオフェンス面。
自分達の形を意識しながらも、前日の感触ほど上手くはいかなかったかんじ。
自分達の形を意識しながらも、前日の感触ほど上手くはいかなかったかんじ。
チームメイト同士のポジション取り距離感や球離れや判断が合ってない。
でもネガティブ要素はポジティブ要素へのヒント。
まぁ、これからまた色々な相手とやって学んでいきましょ。
まぁ、これからまた色々な相手とやって学んでいきましょ。
各メンバーで意見は持ってるから、良くなっていけるはず。
そうそう、形(回し)を決めて取り組むということは、つまり。。
って最近思うことを以下書いておきます。
って最近思うことを以下書いておきます。
簡単な例、それは出し手を決めちゃうというやり方。
ジャンケンでいうところ、最初はグー、あいこなら次はパー、その次はまたグー、そしてパー、以降は交互に繰り返し。
ジャンケンでいうところ、最初はグー、あいこなら次はパー、その次はまたグー、そしてパー、以降は交互に繰り返し。
ここで大事なのは、決めた形(回し)をバカみたいに繰り返す。ってことじゃないのです。
相手が読んできたところ(目線とか表情で読み取る)、そのタイミングでチョキを出す。
これが大事。
ボクシングでいうと。。
ボディブローを打ち込んで、相手のガードが下がってきたところ、ここ一番で顔面に打ち込む。
ボディブローを打ち込んで、相手のガードが下がってきたところ、ここ一番で顔面に打ち込む。
いつまでもボディブローじゃだめ。
そんでもってここ一番で顔面に打ち込んだところ、ふいに相手がカウンターをいれてくるかも。
そしたら、そのまた裏をかいてダブルクロスカウンター。
これを決めないといけない。
こう来たら、こう返す。というレパートリー。
ちなみに矢吹ジョーはトリプルまで入れたのでかなりスゴいです。
こう来たら、こう返す。というレパートリー。
ちなみに矢吹ジョーはトリプルまで入れたのでかなりスゴいです。
こうきたら、こう返す。という意志。
それが戦術というやつ。
だからこそ、将棋の棋譜を読める人は、棋士の戦術を読める、楽しいんだろうなと思う。
だからこそ、将棋の棋譜を読める人は、棋士の戦術を読める、楽しいんだろうなと思う。
話戻って、フットサルで形(回し)を決めるというやり方の楽しみや目的は、相手を型に嵌めさせるというのがひとつと理解してる。
大事なのは、裏をかくタイミングとそのやり方のレパートリー。そのための状況判断と球離れ。
そして、じゃんけんみたいに出し手のパターンが限られているわけではないし、ボクシングみたいに1vs1の関係じゃない。
相手と味方の位置関係をどれだけ見れるか、そしてきっちり選択できるか。
今年frontierZはチームとしては新しい型やセットプレーに取り組んでいる。
個人的にはそのなかで、色んなもらい方の解釈が生まれて、かなり楽しい。
作戦ボードで繰り広げる机上論。
“こうきたら、こう”。
そうだ。
選手と球の動かしかたのルールを決めて交互に指す、そんなフットサルの戦術や球の動かし方の判断を学べるなにかボードゲームみたいなやつがあったら面白そうね。
選手と球の動かしかたのルールを決めて交互に指す、そんなフットサルの戦術や球の動かし方の判断を学べるなにかボードゲームみたいなやつがあったら面白そうね。
ないかな・・考えよう。
あ、気づけば話がだいぶ逸れる、とりとめのない文章でした。
今週末からゴールデンウィーク。
それが空けて少ししたら選手権予選開始。
しまっていこうず。
それが空けて少ししたら選手権予選開始。
しまっていこうず。
いじょー。

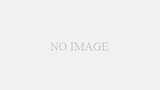
コメント